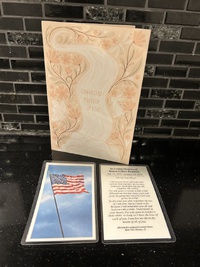2007年03月08日
枕草子 春はあけぼの
春はあけぼの
春はあけぼの。 ようようしろくなり行く、山ぎはすこしあかりて、
むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる。
夏はよる。月の頃はさらなり、やみもなほ、ほたるの多く飛びちがひたる。また、ただひとつふたつなど、ほのかにうちひかりて行くもをかし。雨など降るもをかし。
秋は夕暮。夕日のさして山のはいとちかうなりたるに、からすのねどころへ行くとて、みつよつ、ふたつみつなどとびいそぐさへあはれなり。まいて雁(かり)などのつらねたるが、いとちひさくみゆるはいとをかし。日入りはてて、風の音むしのねなど、はたいふべきにあらず。
冬はつとめて。雪のふりたるはいふべきにもあらず、霜のいとしろきも、またさらでもいと寒きに、火など急ぎおこして、炭もてわたるもいとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火もしろき灰がちになりてわをし。
****************************************
通釈: 枕草子解釈の基礎 志村 士郎著
春は明け方の景色が趣き深い。空がだんだんに、白んでゆく時の山ぎはが、赤みを帯びて、
紫がかった雲が細くたなびいているのはすばらしい
夏は夜が趣きが深い。月のでる頃は言うまでもなくよいが、月のでない夜でも、蛍が入り乱れて飛んでいる光景はやはりすばらしい。また、わずか一匹か二匹ぐらいの蛍が、ほんのりと光ってとんでゆくさまも趣きがある。(そういう夜は)雨などの降るときも趣きがある。
秋は夕暮れの景色が趣き深い。夕日が輝いて、山の稜線に殆ど沈みかかった時に、からすがねぐらへ帰ろうとして、三羽、四羽、又二羽、三羽と群をなして、急ぎ飛んでゆく姿までもしみじみとした感じがする。それにもまして、雁(かり)などが、ならんで飛んでゆくさまが、非常に小さく見えるのはとても趣きがある。太陽がすっかり沈んでしまってからは、風の音や虫のねなどが、また何とも言いようもなくすばらしい。
冬は早朝が趣き深い。雪の降っている時は言いようもなくよいが、霜が真っ白におりている朝も、あるいはまた、霜のおりていない朝も、ひどく寒い時に火などを急いでおこして、それを持ちながら、部屋の前を通って行く姿は、いかにも冬らしく調和がとれた感じがする。昼になてぃ、気温がゆるんでいくと、丸火鉢の火も白いはいが多くなって、感興がそがれるものだ。
****************************************
訳: ゆぐりはいからー (まかびむにー)
春や、ゆーぬあきーがたーぬ、景色がぬーんでぃん、あびららんぐとぅ、いっぺー、上等。
空が、いひなーいひなー、しるくないるばーぬ、うりぬ、やまんかい、あたいんとぅくまが、紅色んかいすまてぃ、紫がかとぅーる雲が、横んかい、ぐなーせんぐあー、ひちゅーせー、いっぺーちゅらはぬならん。
なちや、ゆるが、いっぺえ上等。月がいんじーるくるや、ぬーんあびららんふどぅ上等やしが、月がいんじらんゆるやてぃん、じんじんぬ、あまはいくまはいし、とぅどぅーる、光景や、やっぱり上等やん。また、ふんぬ、てぃーちか、たーちぐぁーぬ、じんじんが、いひぐぁーひからち、とぅでぃいちゅしん、趣きがあん。(うんとぅうゆるや)あみとぅか、ふてぃん上等やん。
秋やひーがうちーる景色が上等。夕日がひかてぃ、やまが空んかいかかいるとぅくま(稜線)んかい、てーげーしじみかかたんとぅきに、からすが、ねぐら(どぅーんやー)んかい、けーいんでぃち、みーち、ゆーち、あらんねー、たーち、みーちんでぃち、むるまじゅい、群なち、あわてぃはーてぃし、とぅでぃいちゅる、姿わーきん、かなはるうみーがすん。(うりんしむしが)うりゆーかー、雁(かり)とぅかが、ならでぃ、とぅでぃいちゅる様子が、いっぺーぐなくみーせー、でーじ趣きがあん。ひーが、しじでぃからー、かじぬうとぅとぅ、虫ぬくぃーぐぁーが、また、ぬーんでぃんあびららんぐとぅ、いっぺー上等。
冬やゆーがあきてぃからがいっぺー上等。雪がふとぅーるばーや、あびーららんふどぅ、上等やしが、霜がまっしるく、うちとぅーる朝ん、やんねーまた、うん霜がうちとぅーかん朝ん、いっぺーひーさん時に、火ーそーなー、あわてぃてぃ、うくち、うり待ちーがちーなー、部屋んめー、とぅーてぃいちゅる、姿や、あんし冬ねーし、調和がとぅりてとぅーる、うみーがすん。昼んかいなてぃ、気温がゆるくなてぃちーねー、丸火鉢ぬ火ーぬ、しるー灰ぐぁが、ううくなてぃ、趣きがねーらん。
****************************************
編通釈: ゆぐりはいからー
春は明け方の景色が情緒深い。空がだんだん、白くなってゆく時の空の、山に接する所が、赤みを帯びて、紫がかった雲が細くたなびいているのはすばらしい
夏は夜が感慨深い。月のでる頃は言うまでもなくよいが、月のでない夜でも、蛍が入り乱れて飛んでいる光景はやはりすばらしい。また、わずか一匹か二匹ぐらいの蛍が、ほんのりと光ってとんでゆく光景も情緒深い。(そういう夜は)雨などの降るときも情緒深い。
秋は夕暮れの景色が情緒深い。夕日が輝いて、山が空に接する部分に殆ど沈みかかった時に、からすがねぐらへ帰ろうとして、三羽、四羽、又二羽、三羽と群をなして、急ぎ飛んでゆく姿までもしみじみとした感じがする。それにもまして、雁(かり)などが、ならんで飛んでゆく光景が、非常に小さく見えるのはとても情緒深い。太陽がすっかり沈んでしまってからは、風の音や虫のねなどが、また何とも言いようもなくすばらしい。
冬は早朝が情緒深い。雪の降っている時は言いようもなくよいが、霜が真っ白におりている朝も、あるいはまた、霜のおりていない朝も、ひどく寒い時に火などを急いでおこして、それを持ちながら、部屋の前を通って行く姿は、いかにも冬らしく調和がとれた感じがする。昼になって、気温があたたかくなると、丸火鉢の火の白い灰が多くなって、今迄の情緒深い観念がが消えてしまう。
春はあけぼの。 ようようしろくなり行く、山ぎはすこしあかりて、
むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる。
夏はよる。月の頃はさらなり、やみもなほ、ほたるの多く飛びちがひたる。また、ただひとつふたつなど、ほのかにうちひかりて行くもをかし。雨など降るもをかし。
秋は夕暮。夕日のさして山のはいとちかうなりたるに、からすのねどころへ行くとて、みつよつ、ふたつみつなどとびいそぐさへあはれなり。まいて雁(かり)などのつらねたるが、いとちひさくみゆるはいとをかし。日入りはてて、風の音むしのねなど、はたいふべきにあらず。
冬はつとめて。雪のふりたるはいふべきにもあらず、霜のいとしろきも、またさらでもいと寒きに、火など急ぎおこして、炭もてわたるもいとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火もしろき灰がちになりてわをし。
****************************************
通釈: 枕草子解釈の基礎 志村 士郎著
春は明け方の景色が趣き深い。空がだんだんに、白んでゆく時の山ぎはが、赤みを帯びて、
紫がかった雲が細くたなびいているのはすばらしい
夏は夜が趣きが深い。月のでる頃は言うまでもなくよいが、月のでない夜でも、蛍が入り乱れて飛んでいる光景はやはりすばらしい。また、わずか一匹か二匹ぐらいの蛍が、ほんのりと光ってとんでゆくさまも趣きがある。(そういう夜は)雨などの降るときも趣きがある。
秋は夕暮れの景色が趣き深い。夕日が輝いて、山の稜線に殆ど沈みかかった時に、からすがねぐらへ帰ろうとして、三羽、四羽、又二羽、三羽と群をなして、急ぎ飛んでゆく姿までもしみじみとした感じがする。それにもまして、雁(かり)などが、ならんで飛んでゆくさまが、非常に小さく見えるのはとても趣きがある。太陽がすっかり沈んでしまってからは、風の音や虫のねなどが、また何とも言いようもなくすばらしい。
冬は早朝が趣き深い。雪の降っている時は言いようもなくよいが、霜が真っ白におりている朝も、あるいはまた、霜のおりていない朝も、ひどく寒い時に火などを急いでおこして、それを持ちながら、部屋の前を通って行く姿は、いかにも冬らしく調和がとれた感じがする。昼になてぃ、気温がゆるんでいくと、丸火鉢の火も白いはいが多くなって、感興がそがれるものだ。
****************************************
訳: ゆぐりはいからー (まかびむにー)
春や、ゆーぬあきーがたーぬ、景色がぬーんでぃん、あびららんぐとぅ、いっぺー、上等。
空が、いひなーいひなー、しるくないるばーぬ、うりぬ、やまんかい、あたいんとぅくまが、紅色んかいすまてぃ、紫がかとぅーる雲が、横んかい、ぐなーせんぐあー、ひちゅーせー、いっぺーちゅらはぬならん。
なちや、ゆるが、いっぺえ上等。月がいんじーるくるや、ぬーんあびららんふどぅ上等やしが、月がいんじらんゆるやてぃん、じんじんぬ、あまはいくまはいし、とぅどぅーる、光景や、やっぱり上等やん。また、ふんぬ、てぃーちか、たーちぐぁーぬ、じんじんが、いひぐぁーひからち、とぅでぃいちゅしん、趣きがあん。(うんとぅうゆるや)あみとぅか、ふてぃん上等やん。
秋やひーがうちーる景色が上等。夕日がひかてぃ、やまが空んかいかかいるとぅくま(稜線)んかい、てーげーしじみかかたんとぅきに、からすが、ねぐら(どぅーんやー)んかい、けーいんでぃち、みーち、ゆーち、あらんねー、たーち、みーちんでぃち、むるまじゅい、群なち、あわてぃはーてぃし、とぅでぃいちゅる、姿わーきん、かなはるうみーがすん。(うりんしむしが)うりゆーかー、雁(かり)とぅかが、ならでぃ、とぅでぃいちゅる様子が、いっぺーぐなくみーせー、でーじ趣きがあん。ひーが、しじでぃからー、かじぬうとぅとぅ、虫ぬくぃーぐぁーが、また、ぬーんでぃんあびららんぐとぅ、いっぺー上等。
冬やゆーがあきてぃからがいっぺー上等。雪がふとぅーるばーや、あびーららんふどぅ、上等やしが、霜がまっしるく、うちとぅーる朝ん、やんねーまた、うん霜がうちとぅーかん朝ん、いっぺーひーさん時に、火ーそーなー、あわてぃてぃ、うくち、うり待ちーがちーなー、部屋んめー、とぅーてぃいちゅる、姿や、あんし冬ねーし、調和がとぅりてとぅーる、うみーがすん。昼んかいなてぃ、気温がゆるくなてぃちーねー、丸火鉢ぬ火ーぬ、しるー灰ぐぁが、ううくなてぃ、趣きがねーらん。
****************************************
編通釈: ゆぐりはいからー
春は明け方の景色が情緒深い。空がだんだん、白くなってゆく時の空の、山に接する所が、赤みを帯びて、紫がかった雲が細くたなびいているのはすばらしい
夏は夜が感慨深い。月のでる頃は言うまでもなくよいが、月のでない夜でも、蛍が入り乱れて飛んでいる光景はやはりすばらしい。また、わずか一匹か二匹ぐらいの蛍が、ほんのりと光ってとんでゆく光景も情緒深い。(そういう夜は)雨などの降るときも情緒深い。
秋は夕暮れの景色が情緒深い。夕日が輝いて、山が空に接する部分に殆ど沈みかかった時に、からすがねぐらへ帰ろうとして、三羽、四羽、又二羽、三羽と群をなして、急ぎ飛んでゆく姿までもしみじみとした感じがする。それにもまして、雁(かり)などが、ならんで飛んでゆく光景が、非常に小さく見えるのはとても情緒深い。太陽がすっかり沈んでしまってからは、風の音や虫のねなどが、また何とも言いようもなくすばらしい。
冬は早朝が情緒深い。雪の降っている時は言いようもなくよいが、霜が真っ白におりている朝も、あるいはまた、霜のおりていない朝も、ひどく寒い時に火などを急いでおこして、それを持ちながら、部屋の前を通って行く姿は、いかにも冬らしく調和がとれた感じがする。昼になって、気温があたたかくなると、丸火鉢の火の白い灰が多くなって、今迄の情緒深い観念がが消えてしまう。
Posted by ゆぐりはいから〜 at 09:18│Comments(3)
│うちなー方言
この記事へのコメント
ゆぐりはいからーさん
『枕草子』の古典のリズムは作者の心の美しさが全部に満ち溢れていますね
四季感のない沖縄では想像のつかない情景が目の前に浮かんでくるような日本独自の情緒ある作品です。
方言の訳もあり、翻訳に基づいた、ゆぐりはいからーさんの個性がちりばめられた現代語訳こそが趣きが深くて何度も読みかえしました
そして高校時代に学んだことを思い出し懐かしさでいっぱいです♪
ノートに書き写して勉強します
どうもありがとう
m(__)m
『枕草子』の古典のリズムは作者の心の美しさが全部に満ち溢れていますね
四季感のない沖縄では想像のつかない情景が目の前に浮かんでくるような日本独自の情緒ある作品です。
方言の訳もあり、翻訳に基づいた、ゆぐりはいからーさんの個性がちりばめられた現代語訳こそが趣きが深くて何度も読みかえしました
そして高校時代に学んだことを思い出し懐かしさでいっぱいです♪
ノートに書き写して勉強します
どうもありがとう
m(__)m
Posted by jeanne・darc at 2007年03月08日 10:16
時間の合間に少しずつノートに記録したら
6ページ半になりました (+_+)
まかびむにーも全部記録したので。
でも行間を1行あけてますからね (^^)
方言の枕草子の訳を読んだのは、初めてです
ゆぐりはいからーさんは知的で勉強家なんだと感心しました。。
6ページ半になりました (+_+)
まかびむにーも全部記録したので。
でも行間を1行あけてますからね (^^)
方言の枕草子の訳を読んだのは、初めてです
ゆぐりはいからーさんは知的で勉強家なんだと感心しました。。
Posted by jeanne・darc at 2007年03月08日 12:15
jeanne・darcさん、
知的だなんて、初めて言われた様な気がします。恐縮です。
遊び心で始めた枕草子の方言の訳、jeanne・darcさんのおっしゃる通り、結構私自身楽しんでたんですよー。これに味をしめて、今度は徒然草などをと思っています(笑)、うそうそ。この訳をした事によって、古典の秘められた魅力を改めて発見致しました。ちゃんと本に書かれているのに、今迄無視していたんですね。枕草子には“省略法”というのが、使われており、それによって私の想像力も豊かになり、この詩に魅了されてしまったんです。jeanne・darcさんのアドバイスも私の編通訳(?)の中で使用させて頂きました。有り難うございました。
知的だなんて、初めて言われた様な気がします。恐縮です。
遊び心で始めた枕草子の方言の訳、jeanne・darcさんのおっしゃる通り、結構私自身楽しんでたんですよー。これに味をしめて、今度は徒然草などをと思っています(笑)、うそうそ。この訳をした事によって、古典の秘められた魅力を改めて発見致しました。ちゃんと本に書かれているのに、今迄無視していたんですね。枕草子には“省略法”というのが、使われており、それによって私の想像力も豊かになり、この詩に魅了されてしまったんです。jeanne・darcさんのアドバイスも私の編通訳(?)の中で使用させて頂きました。有り難うございました。
Posted by ゆぐりはいからー(ブラッサム・チャイルド) at 2007年03月08日 13:01